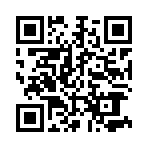2009年10月22日
醤油蔵訪問記
醤油の蔵訪問をしてまいりました。

御殿場の、天野醤油さんです。6月に縁あって、高橋万太郎さんと言う方のお話を聞くことがあったのですが、その時から、県内に残された数少ないこだわりの醤油屋さんとして、天野醤油さんに興味を持ち、夏場は造りがないと言うことで、やっと今回の訪問に至りました。
すでに我が家ではこちらのお醤油を使っているので、美味しいことはわかっていますが、今回訪問して、改めてその醤油の造りの奥の深さに、ますます理解が深まった次第です。
あまり専門的なことをお話してもややこしくなってしまいますが、まずここのこだわりその壱は、天然醸造。
天然醸造で造ると、仕込みを初めてお醤油が出来上がるまでに、一年前後掛かります。造るものによっては二年。自然な醸造方法なので、季節などによって発酵の進み方が変るのだそうです。
大手メーカーは、お得意の効率化で、いろいろな非・自然な工夫をもちいて大幅に製造期間を短縮しているのが実情。
こだわりその弐は、生揚げ醤油であること。生揚げ醤油と言うのは、天然醸造で出来たそのままのお醤油と言うこと。本当に自然なお醤油なんです。これが普通だったはずなんですが。
そのままって、そのままじゃないことってあるのかと言うと、大手の醤油は、食塩水で伸ばしたり、そこで色が薄くなると色をつけたり、あの手この手で造った生揚げ醤油を増量してから製品として出荷しているそうです。

これが発酵中の醤油 濃厚なお醤油の香りがあたりに充満しています
こだわりその参は、原材料。お醤油の原料となる、小麦は県内産、塩は鳴戸の塩、水は、近くに湧き出る富士山の雪解け水、大豆は、本丸亭と言う銘柄のものは、国産丸大豆、それ以外のものは、遺伝子組み換えでない脱脂加工大豆。もちろん、全てに国産丸大豆を使えればそれに越したことはないでしょう、が、それではあまりにコストがかかってしまい、現実的に脱脂加工大豆も使わざる終えないと言うことです。が、それでも、最近は、完全国内原料の本丸亭の需要が、徐々に伸びてきているそうです。
ちなみに、御殿場、三島、沼津の学校給食で使われているお醤油は、この本丸亭なんだそうです。もちろん、蔵も、地域のために一肌脱いで、かなりのご奉仕価格なんですとはおっしゃっていましたが、それでも大手の醤油よりは確実に値が上がってしまいます。それでもこの正しい醤油を使おうという、東部地域の学校給食の栄養士さん、素晴らしい!
今回は、醤油の話で熱くなってしまいましたが、でも考えてみたら、醤油などの調味料、毎日どこかで口にする、とてもとても基本的な調味料です。基本的であると言うことは大切であると言うこと、是非、もっともっと、気を使いましょう。だってとにかく、美味しいんですから。ちなみに長島酒店でも、取り扱いを始めました(ちょっと宣伝)。

御殿場の、天野醤油さんです。6月に縁あって、高橋万太郎さんと言う方のお話を聞くことがあったのですが、その時から、県内に残された数少ないこだわりの醤油屋さんとして、天野醤油さんに興味を持ち、夏場は造りがないと言うことで、やっと今回の訪問に至りました。
すでに我が家ではこちらのお醤油を使っているので、美味しいことはわかっていますが、今回訪問して、改めてその醤油の造りの奥の深さに、ますます理解が深まった次第です。
あまり専門的なことをお話してもややこしくなってしまいますが、まずここのこだわりその壱は、天然醸造。
天然醸造で造ると、仕込みを初めてお醤油が出来上がるまでに、一年前後掛かります。造るものによっては二年。自然な醸造方法なので、季節などによって発酵の進み方が変るのだそうです。
大手メーカーは、お得意の効率化で、いろいろな非・自然な工夫をもちいて大幅に製造期間を短縮しているのが実情。
こだわりその弐は、生揚げ醤油であること。生揚げ醤油と言うのは、天然醸造で出来たそのままのお醤油と言うこと。本当に自然なお醤油なんです。これが普通だったはずなんですが。
そのままって、そのままじゃないことってあるのかと言うと、大手の醤油は、食塩水で伸ばしたり、そこで色が薄くなると色をつけたり、あの手この手で造った生揚げ醤油を増量してから製品として出荷しているそうです。

これが発酵中の醤油 濃厚なお醤油の香りがあたりに充満しています
こだわりその参は、原材料。お醤油の原料となる、小麦は県内産、塩は鳴戸の塩、水は、近くに湧き出る富士山の雪解け水、大豆は、本丸亭と言う銘柄のものは、国産丸大豆、それ以外のものは、遺伝子組み換えでない脱脂加工大豆。もちろん、全てに国産丸大豆を使えればそれに越したことはないでしょう、が、それではあまりにコストがかかってしまい、現実的に脱脂加工大豆も使わざる終えないと言うことです。が、それでも、最近は、完全国内原料の本丸亭の需要が、徐々に伸びてきているそうです。
ちなみに、御殿場、三島、沼津の学校給食で使われているお醤油は、この本丸亭なんだそうです。もちろん、蔵も、地域のために一肌脱いで、かなりのご奉仕価格なんですとはおっしゃっていましたが、それでも大手の醤油よりは確実に値が上がってしまいます。それでもこの正しい醤油を使おうという、東部地域の学校給食の栄養士さん、素晴らしい!
今回は、醤油の話で熱くなってしまいましたが、でも考えてみたら、醤油などの調味料、毎日どこかで口にする、とてもとても基本的な調味料です。基本的であると言うことは大切であると言うこと、是非、もっともっと、気を使いましょう。だってとにかく、美味しいんですから。ちなみに長島酒店でも、取り扱いを始めました(ちょっと宣伝)。
2009年10月22日
おみやげ②
教会とかの特殊なパイプオルガンを演奏され、その関係で、毎年必ず、フランス北部やドイツにいらっしゃるお客様がいらっしゃいます。今回、アルザスのお土産だよーと、ワインをいただきました。(2回目なんです、いつもありがとうございます。。。)

ところで、このワインは、蔵の直売所で購入されたワインと言うことですが、よく、地元消費用は酸化防止剤を入れないんだ、と言う話を聞きます。
確かに、輸送時のワイン劣化の危険性を、酸化防止剤を入れることの理由として挙げる蔵元もいます。なので、あながち的外れではないのかもしれません。が、これは輸入用だから酸化防止剤を入れて、これは地元用だから入れないで、と区別することが、どこまで出来るのか、と言う疑問も残ります。
また、酸化防止剤は、確かに大量使用すると、風味も損なうし、決していいものではありませんが、極少量の場合なら、体に害があることはないですし、この酸化防止剤の正体となる二酸化硫黄と言う物質は、ワインの醸造過程において、アルコール発酵の副産物として極少量自然に発生することもあるようです。つまり、自然の産物。そこまで気にする必要もないかなとも思います。
お土産の話が、おっといつの間にか、ややこしい酸化防止剤の話になってしまいました。
いただいたアルザスのゲヴュルツは、品種特性のよく出た香りに、味わい自体はここ数年の流れにあるスマートなボディーで、すいすいすいーっ と、美味しくいただきました。重ね重ね、ありがとうございました。

ところで、このワインは、蔵の直売所で購入されたワインと言うことですが、よく、地元消費用は酸化防止剤を入れないんだ、と言う話を聞きます。
確かに、輸送時のワイン劣化の危険性を、酸化防止剤を入れることの理由として挙げる蔵元もいます。なので、あながち的外れではないのかもしれません。が、これは輸入用だから酸化防止剤を入れて、これは地元用だから入れないで、と区別することが、どこまで出来るのか、と言う疑問も残ります。
また、酸化防止剤は、確かに大量使用すると、風味も損なうし、決していいものではありませんが、極少量の場合なら、体に害があることはないですし、この酸化防止剤の正体となる二酸化硫黄と言う物質は、ワインの醸造過程において、アルコール発酵の副産物として極少量自然に発生することもあるようです。つまり、自然の産物。そこまで気にする必要もないかなとも思います。
お土産の話が、おっといつの間にか、ややこしい酸化防止剤の話になってしまいました。
いただいたアルザスのゲヴュルツは、品種特性のよく出た香りに、味わい自体はここ数年の流れにあるスマートなボディーで、すいすいすいーっ と、美味しくいただきました。重ね重ね、ありがとうございました。