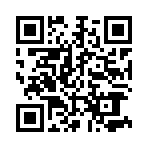2011年01月31日
そろそろ さくら の季節ですね
こんなに寒いのに、何をとんちんかんなことを言っているんだと、怒られてしまいそうですが…

長島酒店では、目下この さくら が満開中。北海道の共働学舎という農場で造られるこのチーズ、本場ヨーロッパのチーズコンクールでも金賞を受賞している、世界基準のおいしい日本のチーズです。
共働学舎代表の宮嶋望さんは、「みんな、神様をつれてやってきた」という本も出していらっしゃいますが、こちらも、とっても面白い本でした。
チーズも本も、ぜひ一度体験していただきたい、素晴らしいものです。
長島酒店では、目下この さくら が満開中。北海道の共働学舎という農場で造られるこのチーズ、本場ヨーロッパのチーズコンクールでも金賞を受賞している、世界基準のおいしい日本のチーズです。
共働学舎代表の宮嶋望さんは、「みんな、神様をつれてやってきた」という本も出していらっしゃいますが、こちらも、とっても面白い本でした。
チーズも本も、ぜひ一度体験していただきたい、素晴らしいものです。
2011年01月27日
こんなお店に行ってきました
東京に出張、春と秋は、セミナーや試飲会が多いのです。
せっかく東京に行ったときには、話題のワインショップや、評判の料理屋さんに寄ってきます。
今回は、ワインインポーターさんのおすすめで、丸の内の、TAMAさんというお店で食事をしてきました。

この洗練された店内、この写真からは想像できませんが、琉球チャイニーズということで、沖縄や中華をアレンジしたお料理です。オーナーさんが沖縄出身で、しかも、琉球人と中国人とのハーフでいらっしゃるということで、納得。
そして、ワインも豊富なのです。この日は、アルザスの白と一緒に、お料理をいただきました。
絶品だったのが、これ。

杏仁豆腐じゃありませんよ、有機野菜の蒸したものを、塩味のスープに入れたもの、ボウルの向こうに見える醤油ベースのたれにつけていただきました。野菜の旨味がたまらない逸品でした。
せっかく東京に行ったときには、話題のワインショップや、評判の料理屋さんに寄ってきます。
今回は、ワインインポーターさんのおすすめで、丸の内の、TAMAさんというお店で食事をしてきました。
この洗練された店内、この写真からは想像できませんが、琉球チャイニーズということで、沖縄や中華をアレンジしたお料理です。オーナーさんが沖縄出身で、しかも、琉球人と中国人とのハーフでいらっしゃるということで、納得。
そして、ワインも豊富なのです。この日は、アルザスの白と一緒に、お料理をいただきました。
絶品だったのが、これ。
杏仁豆腐じゃありませんよ、有機野菜の蒸したものを、塩味のスープに入れたもの、ボウルの向こうに見える醤油ベースのたれにつけていただきました。野菜の旨味がたまらない逸品でした。
2011年01月26日
富士山
富士山が、毎日当たり前に、こんなにきれいに見る事が出来るという幸せ、有難いことです。

これは安倍川の河川敷からの眺め。先日、子供のソフトボールの応援に行った時のものですが、長島酒店の事務所からも、毎日きれいな富士山を、見ることができます。
これは安倍川の河川敷からの眺め。先日、子供のソフトボールの応援に行った時のものですが、長島酒店の事務所からも、毎日きれいな富士山を、見ることができます。
2011年01月21日
もっともっと甘口ワインを
なぜ、日本のワイン消費者は、甘口ワインを避けるのでしょうか。
ワインの伝統国がひしめくヨーロッパでは、甘口ワインが、普通に消費されています。ご近所のフランス人も、いろいろワインを買っていかれますが、甘口もよく選んでいらっしゃいます。
何か、日本では、甘口ワインは素人っぽい、そんなイメージがあるんでしょうか、積極的に飲む方が、非常に少数派です。
でも、でも、本来、日本の食卓では、やや甘口のワインなどが、日々のお惣菜と抜群に相性がよく、きっと、赤ワインを飲むよりも、食卓での楽しさも大きいんじゃないかなと、私は常々思っております。

昨夜のワインは、ドイツのラインガウのワイン、ハルガルテナー・ユンクファー・シュペトレーゼ・2002、造り手は、プリンツ。晩のおかずは、豚肉のお料理や、いんげんと厚揚げを中華風に甘辛く炒めたものと、サラダなど、どれもワインとの相性がよく、とても楽しめました。
先入観を捨てて、もっともっと、自由にワインを飲みましょう。もっともっと、ワインの楽しさ、広がります。
ワインの伝統国がひしめくヨーロッパでは、甘口ワインが、普通に消費されています。ご近所のフランス人も、いろいろワインを買っていかれますが、甘口もよく選んでいらっしゃいます。
何か、日本では、甘口ワインは素人っぽい、そんなイメージがあるんでしょうか、積極的に飲む方が、非常に少数派です。
でも、でも、本来、日本の食卓では、やや甘口のワインなどが、日々のお惣菜と抜群に相性がよく、きっと、赤ワインを飲むよりも、食卓での楽しさも大きいんじゃないかなと、私は常々思っております。
昨夜のワインは、ドイツのラインガウのワイン、ハルガルテナー・ユンクファー・シュペトレーゼ・2002、造り手は、プリンツ。晩のおかずは、豚肉のお料理や、いんげんと厚揚げを中華風に甘辛く炒めたものと、サラダなど、どれもワインとの相性がよく、とても楽しめました。
先入観を捨てて、もっともっと、自由にワインを飲みましょう。もっともっと、ワインの楽しさ、広がります。
2011年01月18日
ずらり新着、そしてイベントのご案内

ずらりと並んだ新着ワイン。12月に入っていましたが、イタリアから長く船旅で揺られてきているので、現在長島酒店のワイン保管庫でお休み中。
全てイタリアです。
そして、全て小さな農家さんが自然に栽培した葡萄をつかって造った手造りワインです。
もうちょっとお休みさせてから、下記のイベントにて、デビューさせようと思っています。
そのイベントとは
「浮月楼でワインパーティー 平成23年春」
日時 平成23年2月9日(水) 18:00~20:00
会場 浮月楼様内 カフェ・ライフタイム
定員 30人
会費 3000円
写真のワイン以外にも、イタリアの農家さん手造りワインをまだまだたくさん、総数およそ25から30アイテムくらいになると思います、今回は、とにかくイタリアワインです。オードブルがついて、ワインがこれだけ飲めて3000円は、お気軽で楽しいでしょ。毎回大好評です。
お申し込みは、長島酒店まで、電話054-245-9260です。
お申し込みお待ちしております。
2011年01月16日
ワインの常識を考える①-2
昨日は、ワインは本当に、開けたらその日のうちに飲まなければならないのか、ということについて、決してその日に飲みきってしまわなくても構わないと思う、という私の意見を述べさせていただきました。
本日はその続きです。
さて、一度コルクを抜いてしまったら、ワインの味わいはどうなるのでしょうか。
私の経験では、翌日に品質が落ちてしまうワインなど、そうそうありません。それどころか、なんかバランス悪いなぁ、と思うワインが、数日後に、とてもバランスの良いワインに変る事もありました。そうは言っても、たまには、確かに、二日目、三日目とどんどん下がっていくワインもないわけではありません。
ここでちょっと脱線しますが、私の、我が家での晩酌の実態です。実はここ2年くらいは、焼津のTさんの影響で、常に、同時に何本かの飲みかけのワインや日本酒が、キッチンの一角に陣取っております。その日のメニューによって、臨機応変に、飲み分けられています。一度の食事の途中で、ワインから日本酒に交代、なんてこともよくあります。これに関しては、私、非常にフットワーク軽いです。
話は戻って、開けてから何日もおいしさを保つワインと、2日目くらいから落ちて行ってしまうワインの違い、その違いは、もとになる葡萄の質のによるのではないかと思うのです。自然環境を尊重して正しく育てられた葡萄から造られたワインは、元の葡萄が力強いエネルギー溢れるものだと、そのワインも、栓を抜いてからもしっかりしているのではないでしょうか。確かに変化はします。しかし、悪くなるのとは意味が違います。
それでは、もう飲めない、と感じるのはどんなときでしょう。これは明確な規定があるわけではありませんが、私の感覚としては、果実味を感じなくなってしまった時点で、そのワインの寿命が終ったなぁ、と、私は判断します。
それ以外に栓を抜いてからのワインの持ちに関係してくるのは、そのワインの年齢でしょう。やはりある程度すでに瓶内で熟成しているワインは、栓を抜いてからの変化は早いし、果実味が無くなってしまうのも早いのは否めませんね。
先程、あけて翌日には品質の落ちてしまうワインなどそうそうありません、と書きましたが、それは、私が意識的に、そのような健全なワインを多く選んで仕入れているからだと思います。やはり農薬などを多用している畑で採れた葡萄で、工業的に造られたワインは(いまだに世の中の多くのワインはそんなワインです)、日持ちが悪いような気がします。天然健康優良児と、ビタミン剤などの人工的な栄養漬けで過保護に育てられた子供と、どちらが強いか考えてみれば明白ですね。
ワインは、開けたらその日のうちに飲まなくてはならない、という間違った先入観を捨ててしまえば、その日の体調や、晩の献立に合せて、ワインや地酒を選ぶ楽しみが増えますよ。
健全なワイン、健全な地酒で、楽しい晩酌を!

ウイヤージュなしで5年間樽熟させてから出荷された、ミッシェル・オジェさんのニューアイテム、ヴァン・ド・ヴォワル。ヴォワルは、酸膜酵母にも掛けられているんですね、きっと。フランスのダジャレですか…
本日はその続きです。
さて、一度コルクを抜いてしまったら、ワインの味わいはどうなるのでしょうか。
私の経験では、翌日に品質が落ちてしまうワインなど、そうそうありません。それどころか、なんかバランス悪いなぁ、と思うワインが、数日後に、とてもバランスの良いワインに変る事もありました。そうは言っても、たまには、確かに、二日目、三日目とどんどん下がっていくワインもないわけではありません。
ここでちょっと脱線しますが、私の、我が家での晩酌の実態です。実はここ2年くらいは、焼津のTさんの影響で、常に、同時に何本かの飲みかけのワインや日本酒が、キッチンの一角に陣取っております。その日のメニューによって、臨機応変に、飲み分けられています。一度の食事の途中で、ワインから日本酒に交代、なんてこともよくあります。これに関しては、私、非常にフットワーク軽いです。
話は戻って、開けてから何日もおいしさを保つワインと、2日目くらいから落ちて行ってしまうワインの違い、その違いは、もとになる葡萄の質のによるのではないかと思うのです。自然環境を尊重して正しく育てられた葡萄から造られたワインは、元の葡萄が力強いエネルギー溢れるものだと、そのワインも、栓を抜いてからもしっかりしているのではないでしょうか。確かに変化はします。しかし、悪くなるのとは意味が違います。
それでは、もう飲めない、と感じるのはどんなときでしょう。これは明確な規定があるわけではありませんが、私の感覚としては、果実味を感じなくなってしまった時点で、そのワインの寿命が終ったなぁ、と、私は判断します。
それ以外に栓を抜いてからのワインの持ちに関係してくるのは、そのワインの年齢でしょう。やはりある程度すでに瓶内で熟成しているワインは、栓を抜いてからの変化は早いし、果実味が無くなってしまうのも早いのは否めませんね。
先程、あけて翌日には品質の落ちてしまうワインなどそうそうありません、と書きましたが、それは、私が意識的に、そのような健全なワインを多く選んで仕入れているからだと思います。やはり農薬などを多用している畑で採れた葡萄で、工業的に造られたワインは(いまだに世の中の多くのワインはそんなワインです)、日持ちが悪いような気がします。天然健康優良児と、ビタミン剤などの人工的な栄養漬けで過保護に育てられた子供と、どちらが強いか考えてみれば明白ですね。
ワインは、開けたらその日のうちに飲まなくてはならない、という間違った先入観を捨ててしまえば、その日の体調や、晩の献立に合せて、ワインや地酒を選ぶ楽しみが増えますよ。
健全なワイン、健全な地酒で、楽しい晩酌を!
ウイヤージュなしで5年間樽熟させてから出荷された、ミッシェル・オジェさんのニューアイテム、ヴァン・ド・ヴォワル。ヴォワルは、酸膜酵母にも掛けられているんですね、きっと。フランスのダジャレですか…
2011年01月15日
ワインの常識を考える①
ブログの内容が今までと少し違うかもしれません、が、ワインにご興味あるある方、読んでいただけば興味深い内容かと思います。
そして、ワインを飲んでみたいけれども、ちょっと敷居が高くて…
こんな方、ぜひ読んでいただければ幸いです。
「ワインは、あけたらその日のうちに飲まないとだめなんですよねぇ」
店頭で、お客様に、こんな質問をよくいただきます。
これに対して、私は、「いや、基本的にそんな事はありませんよ」とお答えします。
実は私も数年前まで、やっぱりあけたらその日に飲まないとだめだと思っていました。体力的にも1本くらい飲めてしまったので、開ければその日に飲みきってしまうようにしていました。あるいは、残す場合は、長島酒店でも売っていますが、瓶の中を真空にするとか、不活性ガスを注入するとか、何らかの保存器具を使っておりました。
しかし、あることをきっかけに、それに疑問を持つようになってしまったのです。
それは、ある時訪問した、フランスの造り手さんの醸造所での試飲の時の事。
「このワインは30日前にあけたものなんだ」と言う説明の後試飲したそのワインの味わいは・・・ 驚きました。全くへたっていません。その造り手さんは、特に自然ブドウ栽培に関しては、フランスでも指導者的な立場にある人で、言って見れば栽培の達人です。そして思いました。生命力溢れる葡萄からできたワインは、栓を抜いたからと言って、そう簡単に風味が落ちるものじゃないんじゃないかと。
そんな驚きの体験をして(やはり体感するのが一番説得力あります)、飲みかけのワインに余計な事をするのを止めました。するのは、もう一度栓をしておく事だけです。
ちょっと長いので、本日はここまで。続きは明日に。

これが、驚きの体験をしている、まさにその時。ロワールの、ドメーヌ・メゾン・ブリュレにて
そして、ワインを飲んでみたいけれども、ちょっと敷居が高くて…
こんな方、ぜひ読んでいただければ幸いです。
「ワインは、あけたらその日のうちに飲まないとだめなんですよねぇ」
店頭で、お客様に、こんな質問をよくいただきます。
これに対して、私は、「いや、基本的にそんな事はありませんよ」とお答えします。
実は私も数年前まで、やっぱりあけたらその日に飲まないとだめだと思っていました。体力的にも1本くらい飲めてしまったので、開ければその日に飲みきってしまうようにしていました。あるいは、残す場合は、長島酒店でも売っていますが、瓶の中を真空にするとか、不活性ガスを注入するとか、何らかの保存器具を使っておりました。
しかし、あることをきっかけに、それに疑問を持つようになってしまったのです。
それは、ある時訪問した、フランスの造り手さんの醸造所での試飲の時の事。
「このワインは30日前にあけたものなんだ」と言う説明の後試飲したそのワインの味わいは・・・ 驚きました。全くへたっていません。その造り手さんは、特に自然ブドウ栽培に関しては、フランスでも指導者的な立場にある人で、言って見れば栽培の達人です。そして思いました。生命力溢れる葡萄からできたワインは、栓を抜いたからと言って、そう簡単に風味が落ちるものじゃないんじゃないかと。
そんな驚きの体験をして(やはり体感するのが一番説得力あります)、飲みかけのワインに余計な事をするのを止めました。するのは、もう一度栓をしておく事だけです。
ちょっと長いので、本日はここまで。続きは明日に。
これが、驚きの体験をしている、まさにその時。ロワールの、ドメーヌ・メゾン・ブリュレにて
Posted by ながしま at
16:21
│Comments(0)
2011年01月14日
必ずしも、大きいグラスがいいとは限らない…
基本的に、ワインの味を見るときは、最初の1杯は、必ず国際規格テイスティンググラスで味を見ます。
ワインに限らずすべての飲み物は、使うグラスによって、大分味わいの印象が変わってしまいます。ですから、最初の1杯は、必ず同じグラスで味を見るようにするのです。
そして同時に、その最初の1杯で、これはデキャンタしたほうがよさそうだ、とか、もう数日おいておこう、とか、考えながら、2杯目以降、どのグラスを使うかも考えてみます。
ボルドーに関しては、大体が、ボルドーグラスを選択すれば問題ありません。が、今回ばかりは、そうではない結果となりました。

グリュオ・ラローズのセカンド、サルジェ・ド・グリュオ・ラローズ・1997。
しっかり果実味はあります。柔らかく熟成した、ふわっと小ぶりの果実味。おいしいです。よし、大きなグラスで飲んでみよう、とグラスを替えたら… あらあらら、小ぶりの果実味が大きなグラスの中で、拡散してしまった感じ、味わいが散漫になってしまったのです。
必ずしも大きなグラスがいいとは限らない、非常に勉強になりました。
小ぶりながら非常に育ちが良い味わいのワインで、やっぱりボルドーの古酒はうまいなぁ。。。 実は底に2センチほど残ったものを、3日後に飲んでみたのですが、全く果実味がへたってませんでした。セカンドとはいえ、グランクリュの実力を垣間見せてくれました。
ワインに限らずすべての飲み物は、使うグラスによって、大分味わいの印象が変わってしまいます。ですから、最初の1杯は、必ず同じグラスで味を見るようにするのです。
そして同時に、その最初の1杯で、これはデキャンタしたほうがよさそうだ、とか、もう数日おいておこう、とか、考えながら、2杯目以降、どのグラスを使うかも考えてみます。
ボルドーに関しては、大体が、ボルドーグラスを選択すれば問題ありません。が、今回ばかりは、そうではない結果となりました。
グリュオ・ラローズのセカンド、サルジェ・ド・グリュオ・ラローズ・1997。
しっかり果実味はあります。柔らかく熟成した、ふわっと小ぶりの果実味。おいしいです。よし、大きなグラスで飲んでみよう、とグラスを替えたら… あらあらら、小ぶりの果実味が大きなグラスの中で、拡散してしまった感じ、味わいが散漫になってしまったのです。
必ずしも大きなグラスがいいとは限らない、非常に勉強になりました。
小ぶりながら非常に育ちが良い味わいのワインで、やっぱりボルドーの古酒はうまいなぁ。。。 実は底に2センチほど残ったものを、3日後に飲んでみたのですが、全く果実味がへたってませんでした。セカンドとはいえ、グランクリュの実力を垣間見せてくれました。
2011年01月13日
安倍川もち
まだ、安倍川もち食べたことがないんだ…
と、二男が言うものですから、静岡に住んでいながら、それはまずい、と言うことで、安倍川もちを食べに行ってきました。

行ったのは、登呂遺跡の隣にある「もちの家」、20年ほど前に行って、とてもおいしかった印象が残っていたので、まだあるかなーと、少し心配しつつ昔の記憶を頼りに行ってみたのですが、あった、良かったぁ。
店の中も昔とほとんど変わっていないと思います、趣のある日本家屋、そして頼んだ安倍川もちも、やはり搗きたてのおもちで造った安倍川もちは違いますね、うまいです、本当に。

徳川家康が名付け親だという静岡名物安倍川もち、シンプルだけれどおいしい。シンプルだからこそ、黄な粉とかもちの質が大切ですね。駅の売店のものとは全くおいしさが違いますよ。
と、二男が言うものですから、静岡に住んでいながら、それはまずい、と言うことで、安倍川もちを食べに行ってきました。
行ったのは、登呂遺跡の隣にある「もちの家」、20年ほど前に行って、とてもおいしかった印象が残っていたので、まだあるかなーと、少し心配しつつ昔の記憶を頼りに行ってみたのですが、あった、良かったぁ。
店の中も昔とほとんど変わっていないと思います、趣のある日本家屋、そして頼んだ安倍川もちも、やはり搗きたてのおもちで造った安倍川もちは違いますね、うまいです、本当に。
徳川家康が名付け親だという静岡名物安倍川もち、シンプルだけれどおいしい。シンプルだからこそ、黄な粉とかもちの質が大切ですね。駅の売店のものとは全くおいしさが違いますよ。
2011年01月12日
駿河酒造場
駿河酒造場
まだ皆さん、初めて聞くよその名前、という方多いんじゃないでしょうか。昨年夏、駿河区西脇に新しくできた日本酒の蔵です。
しかし新しくできたとは言っても、実は戦前から続く萩錦酒造の流れを汲む蔵元であり、実はここに来る前は、造りをやめていた、掛川の曽我鶴酒造の場所を借りて、萩の蔵の名前で数年間酒を造っていたりと、すでに実績はあるんですが。
諸事情により、曽我鶴さんを出ることになって、たまたま、ちょうど蔵を閉めた静岡市の忠正を造っていた吉屋酒造さんの設備を買い取って、西脇に、醸造所を造って、この冬から新たに酒造りが始まった、という次第です。
39歳の若い杜氏さんが造る、日本一新しい酒造場、なんか、楽しみじゃないですか!
近日中に、長島酒店にも、しぼりたての純米が入荷予定です。乞うご期待!
そうでした、肝心な酒の銘柄名ですが、天虹(テンコウ)です。

ほかの設備は忠正さんからのものが多いですが、さすがに麹室だけは、新品ですね。
まだ皆さん、初めて聞くよその名前、という方多いんじゃないでしょうか。昨年夏、駿河区西脇に新しくできた日本酒の蔵です。
しかし新しくできたとは言っても、実は戦前から続く萩錦酒造の流れを汲む蔵元であり、実はここに来る前は、造りをやめていた、掛川の曽我鶴酒造の場所を借りて、萩の蔵の名前で数年間酒を造っていたりと、すでに実績はあるんですが。
諸事情により、曽我鶴さんを出ることになって、たまたま、ちょうど蔵を閉めた静岡市の忠正を造っていた吉屋酒造さんの設備を買い取って、西脇に、醸造所を造って、この冬から新たに酒造りが始まった、という次第です。
39歳の若い杜氏さんが造る、日本一新しい酒造場、なんか、楽しみじゃないですか!
近日中に、長島酒店にも、しぼりたての純米が入荷予定です。乞うご期待!
そうでした、肝心な酒の銘柄名ですが、天虹(テンコウ)です。
ほかの設備は忠正さんからのものが多いですが、さすがに麹室だけは、新品ですね。
2011年01月08日
店舗お休みのお知らせ
いつもありがとうございます。
それでは、早速ですがお知らせです。
1月10日月曜日(祝日)
お店をお休みとさせていただきます。
この前休んだばっかじゃないか・・・ と、怒られそうですが、もう1日くらい、お休みさせていただいてもよろしいでしょうか。
メリハリつけて、また11日からバリバリ頑張りますので。
何卒よろしくお願いいたします。
本日のおまけの写真

パリの超有名ワインショップ、カーヴ・オジェの店頭で。
ながしま、すっかりおのぼりさんの観光客となっています。
それでは、早速ですがお知らせです。
1月10日月曜日(祝日)
お店をお休みとさせていただきます。
この前休んだばっかじゃないか・・・ と、怒られそうですが、もう1日くらい、お休みさせていただいてもよろしいでしょうか。
メリハリつけて、また11日からバリバリ頑張りますので。
何卒よろしくお願いいたします。
本日のおまけの写真
パリの超有名ワインショップ、カーヴ・オジェの店頭で。
ながしま、すっかりおのぼりさんの観光客となっています。
2011年01月06日
まだまだいけました!
毎年12月31日は、特別なワインを開けます。
先日の大晦日に明けたのは、これ

栓を抜くのがもったいなくて、ずっとしまってあったのですが、このようなワイン、なかなか飲むタイミングがなく、1999年のロゼだし、そろそろ飲んであげなくては… と、思い切ってあけました。
もう駄目かもしれないな ・・・ そんな気持ちで栓を抜きましたが、まだまだしっかり果実味は残っており、さすがだー 感心しながら、心地よく一本空いてしまいました。コルクの形が、片方が広い円錐形、おそらく微発砲だったのでしょうね。きもーち、こまあーかい泡がちょびちょびっと残っている感じがしました。
何かものすごくインパクトがあるワインではありませんが、11年たっても素直で心安らぐうまみと果実味のあるロゼワイン、いいワインを飲んだ平成22年の大晦日でした。
先日の大晦日に明けたのは、これ
栓を抜くのがもったいなくて、ずっとしまってあったのですが、このようなワイン、なかなか飲むタイミングがなく、1999年のロゼだし、そろそろ飲んであげなくては… と、思い切ってあけました。
もう駄目かもしれないな ・・・ そんな気持ちで栓を抜きましたが、まだまだしっかり果実味は残っており、さすがだー 感心しながら、心地よく一本空いてしまいました。コルクの形が、片方が広い円錐形、おそらく微発砲だったのでしょうね。きもーち、こまあーかい泡がちょびちょびっと残っている感じがしました。
何かものすごくインパクトがあるワインではありませんが、11年たっても素直で心安らぐうまみと果実味のあるロゼワイン、いいワインを飲んだ平成22年の大晦日でした。
2011年01月05日
長島家の初詣
いつからでしょう、我が家の初詣は、ずっと身延山の久遠寺です。特に日蓮宗とかではないんですが、あのお寺、その周りの空気全体が、なんとなく好きで、毎年初詣となると、自然とこちらに向かってしまいます。
山門をくぐってからの参道が、かなり急な石の階段で(正確には、菩提梯というらしいです)、これを目の前にすると、俄然やる気がわいてくるんです。かなりハードです。こんなに続く急な角度の石の階段にはそうめったにお目にかかりません。

ここを登りきると正面に、

ドカーンと本堂です。
帰りには、52号線沿いの道の駅で、いでぼく直営のお店でソフトクリームを買って、これが、とっても美味しくて、子供たちはこれがないとついてこないかもしれませんね。。。
元旦から3日まで店を開けていましたので、昨日が長島家の初詣、こんな感じでした!
山門をくぐってからの参道が、かなり急な石の階段で(正確には、菩提梯というらしいです)、これを目の前にすると、俄然やる気がわいてくるんです。かなりハードです。こんなに続く急な角度の石の階段にはそうめったにお目にかかりません。
ここを登りきると正面に、
ドカーンと本堂です。
帰りには、52号線沿いの道の駅で、いでぼく直営のお店でソフトクリームを買って、これが、とっても美味しくて、子供たちはこれがないとついてこないかもしれませんね。。。
元旦から3日まで店を開けていましたので、昨日が長島家の初詣、こんな感じでした!
2011年01月02日
あけましておめでとうございます。
もう1月2日なんですが…
今年は段取りよく行こうと思っているのですが、新年のご挨拶が、2日になってしまいまして、恐縮です。
しかし、今年も、おいしいワインや地酒を皆様に飲んでいただいて、たくさんの笑顔を増やすことができるように、張り切って、楽しく仕事をしていきます。
どうぞ皆様今年もよろしくお願いいたします。
ところで、まだ皆様にご紹介していなかったかもしれません、長島酒店の新しいロゴです。かわいいでしょ。。。

今年は段取りよく行こうと思っているのですが、新年のご挨拶が、2日になってしまいまして、恐縮です。
しかし、今年も、おいしいワインや地酒を皆様に飲んでいただいて、たくさんの笑顔を増やすことができるように、張り切って、楽しく仕事をしていきます。
どうぞ皆様今年もよろしくお願いいたします。
ところで、まだ皆様にご紹介していなかったかもしれません、長島酒店の新しいロゴです。かわいいでしょ。。。

Posted by ながしま at
17:03
│Comments(2)