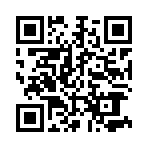2011年01月16日
ワインの常識を考える①-2
昨日は、ワインは本当に、開けたらその日のうちに飲まなければならないのか、ということについて、決してその日に飲みきってしまわなくても構わないと思う、という私の意見を述べさせていただきました。
本日はその続きです。
さて、一度コルクを抜いてしまったら、ワインの味わいはどうなるのでしょうか。
私の経験では、翌日に品質が落ちてしまうワインなど、そうそうありません。それどころか、なんかバランス悪いなぁ、と思うワインが、数日後に、とてもバランスの良いワインに変る事もありました。そうは言っても、たまには、確かに、二日目、三日目とどんどん下がっていくワインもないわけではありません。
ここでちょっと脱線しますが、私の、我が家での晩酌の実態です。実はここ2年くらいは、焼津のTさんの影響で、常に、同時に何本かの飲みかけのワインや日本酒が、キッチンの一角に陣取っております。その日のメニューによって、臨機応変に、飲み分けられています。一度の食事の途中で、ワインから日本酒に交代、なんてこともよくあります。これに関しては、私、非常にフットワーク軽いです。
話は戻って、開けてから何日もおいしさを保つワインと、2日目くらいから落ちて行ってしまうワインの違い、その違いは、もとになる葡萄の質のによるのではないかと思うのです。自然環境を尊重して正しく育てられた葡萄から造られたワインは、元の葡萄が力強いエネルギー溢れるものだと、そのワインも、栓を抜いてからもしっかりしているのではないでしょうか。確かに変化はします。しかし、悪くなるのとは意味が違います。
それでは、もう飲めない、と感じるのはどんなときでしょう。これは明確な規定があるわけではありませんが、私の感覚としては、果実味を感じなくなってしまった時点で、そのワインの寿命が終ったなぁ、と、私は判断します。
それ以外に栓を抜いてからのワインの持ちに関係してくるのは、そのワインの年齢でしょう。やはりある程度すでに瓶内で熟成しているワインは、栓を抜いてからの変化は早いし、果実味が無くなってしまうのも早いのは否めませんね。
先程、あけて翌日には品質の落ちてしまうワインなどそうそうありません、と書きましたが、それは、私が意識的に、そのような健全なワインを多く選んで仕入れているからだと思います。やはり農薬などを多用している畑で採れた葡萄で、工業的に造られたワインは(いまだに世の中の多くのワインはそんなワインです)、日持ちが悪いような気がします。天然健康優良児と、ビタミン剤などの人工的な栄養漬けで過保護に育てられた子供と、どちらが強いか考えてみれば明白ですね。
ワインは、開けたらその日のうちに飲まなくてはならない、という間違った先入観を捨ててしまえば、その日の体調や、晩の献立に合せて、ワインや地酒を選ぶ楽しみが増えますよ。
健全なワイン、健全な地酒で、楽しい晩酌を!

ウイヤージュなしで5年間樽熟させてから出荷された、ミッシェル・オジェさんのニューアイテム、ヴァン・ド・ヴォワル。ヴォワルは、酸膜酵母にも掛けられているんですね、きっと。フランスのダジャレですか…
本日はその続きです。
さて、一度コルクを抜いてしまったら、ワインの味わいはどうなるのでしょうか。
私の経験では、翌日に品質が落ちてしまうワインなど、そうそうありません。それどころか、なんかバランス悪いなぁ、と思うワインが、数日後に、とてもバランスの良いワインに変る事もありました。そうは言っても、たまには、確かに、二日目、三日目とどんどん下がっていくワインもないわけではありません。
ここでちょっと脱線しますが、私の、我が家での晩酌の実態です。実はここ2年くらいは、焼津のTさんの影響で、常に、同時に何本かの飲みかけのワインや日本酒が、キッチンの一角に陣取っております。その日のメニューによって、臨機応変に、飲み分けられています。一度の食事の途中で、ワインから日本酒に交代、なんてこともよくあります。これに関しては、私、非常にフットワーク軽いです。
話は戻って、開けてから何日もおいしさを保つワインと、2日目くらいから落ちて行ってしまうワインの違い、その違いは、もとになる葡萄の質のによるのではないかと思うのです。自然環境を尊重して正しく育てられた葡萄から造られたワインは、元の葡萄が力強いエネルギー溢れるものだと、そのワインも、栓を抜いてからもしっかりしているのではないでしょうか。確かに変化はします。しかし、悪くなるのとは意味が違います。
それでは、もう飲めない、と感じるのはどんなときでしょう。これは明確な規定があるわけではありませんが、私の感覚としては、果実味を感じなくなってしまった時点で、そのワインの寿命が終ったなぁ、と、私は判断します。
それ以外に栓を抜いてからのワインの持ちに関係してくるのは、そのワインの年齢でしょう。やはりある程度すでに瓶内で熟成しているワインは、栓を抜いてからの変化は早いし、果実味が無くなってしまうのも早いのは否めませんね。
先程、あけて翌日には品質の落ちてしまうワインなどそうそうありません、と書きましたが、それは、私が意識的に、そのような健全なワインを多く選んで仕入れているからだと思います。やはり農薬などを多用している畑で採れた葡萄で、工業的に造られたワインは(いまだに世の中の多くのワインはそんなワインです)、日持ちが悪いような気がします。天然健康優良児と、ビタミン剤などの人工的な栄養漬けで過保護に育てられた子供と、どちらが強いか考えてみれば明白ですね。
ワインは、開けたらその日のうちに飲まなくてはならない、という間違った先入観を捨ててしまえば、その日の体調や、晩の献立に合せて、ワインや地酒を選ぶ楽しみが増えますよ。
健全なワイン、健全な地酒で、楽しい晩酌を!
ウイヤージュなしで5年間樽熟させてから出荷された、ミッシェル・オジェさんのニューアイテム、ヴァン・ド・ヴォワル。ヴォワルは、酸膜酵母にも掛けられているんですね、きっと。フランスのダジャレですか…